葬儀に関わる言葉の中には、普段あまり
意識しないけれど、実はきちんと意味が
使い分けられているものがあります。
その代表的なものが、**「棺(ひつぎ)」と
「柩(ひつぎ)」**です。
一般的に「棺」は、まだ空の状態の箱を
指します。
つまり、これから故人をお納めするための
入れ物です。
一方、「柩」は、故人がすでに納められた
状態のものを指します。
そのため、納棺の儀式を終えたあとは、棺が
柩に変わる、とも言えるでしょう。
この違いは、漢字の意味や成り立ちにもしっかり
と表れています。
また、葬儀に関わる専門職や車両にも、この字が
活かされています。
例えば「納棺師」は、故人を美しく整え、棺に
お納めする専門の方です。
ここではまだ「棺」が使われています。
そして「霊柩車」は、故人が納められた「柩」を
運ぶ車です。
ここで初めて「柩」の字が登場するのです。
同じように見える漢字でも、使われる
タイミングや意味を知ると、葬儀の場面での
言葉の深みが感じられます。
葬儀は、人生の最期にふさわしい時間を作る
ためのものです。
言葉一つにも、長い歴史の中で培われてきた
敬意や思いやりが込められています。
トワ家族葬ホール岩国では、そんな言葉や
所作の一つひとつを大切にしながら、最後の
お別れの時間をお手伝いしています。
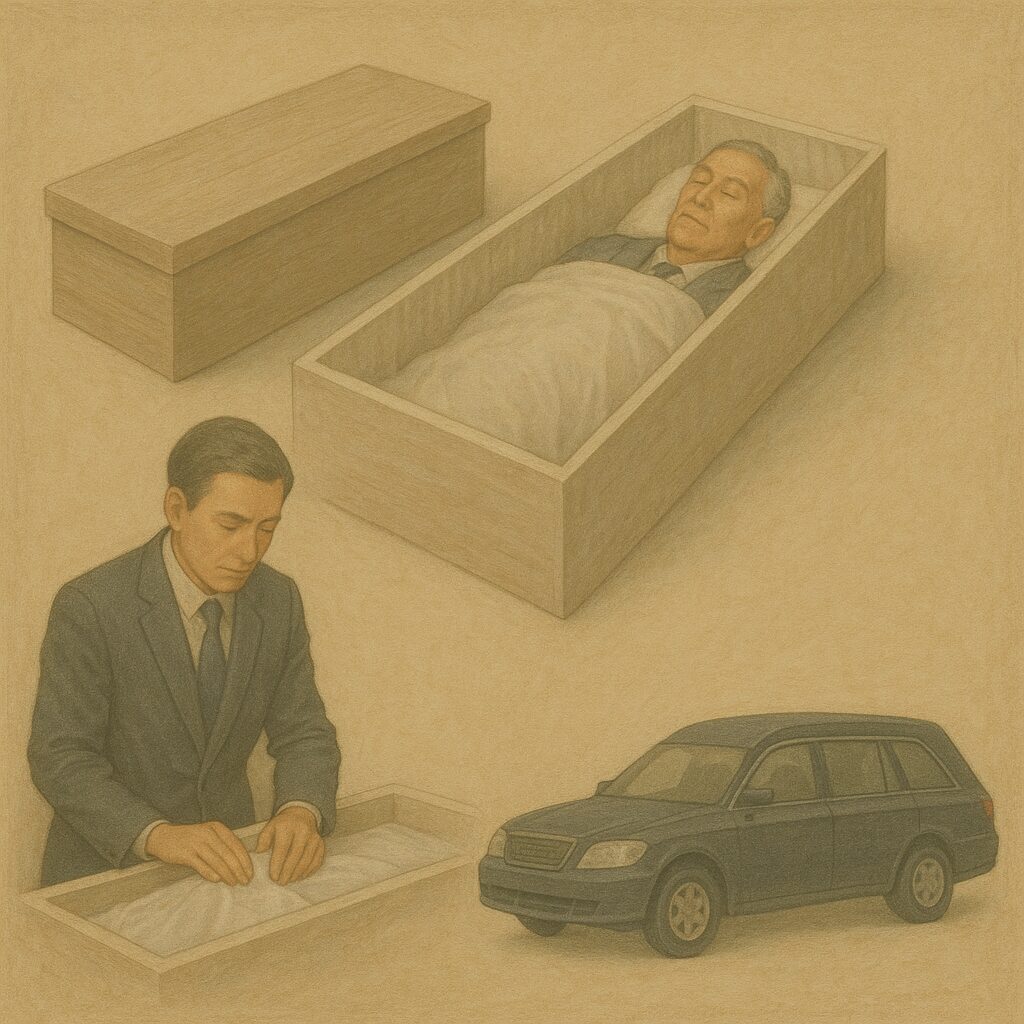
感謝。