いまの葬儀からは想像できない「野辺送り」
の時代
現代のお葬式は、ほとんどが葬儀会館で行われ、
火葬場も整備され、すべてがスムーズで静かに
進みます。
しかし、少し昔──
私たちの祖父の時代までは、葬儀は今とは
まったく違う姿をしていました。
今日は、その「昔の葬儀」について少し
お話ししたいと思います。
⸻
■ 山へ向かって歩く葬列
かつては、自宅で納棺をしたあと、ご家族・
親戚・地域の人たちが集まり、ゆっくりと山に
ある火葬地へ向かって歩きました。
この道中を「葬列(そうれつ)」といい、棺を
担いで歩く「野辺送り(のべおくり)」が
当たり前でした。
かつては村全体で協力し、若い男性たちが
交代で棺を担ぎ、女性は荷物や供物を持ち、
年配の方はその後ろを静かに歩く。
そんな光景が、どこの地域でも見られました。
⸻
■ 道中で響くお経
葬列の途中、僧侶が歩きながら読経をする
こともありました。
いまのように「式場 → 火葬場」ではなく、
山道そのものが“葬儀の場”だったのです。
風の音、山の匂い、足音、読経の声…。
私たちが日々見ている現代のお葬式とは、
まったく違う世界がそこに広がっていました。
⸻
■ 丸一日かかった火葬
今のような火葬炉が無かった時代は、木や藁を
使って火をつけ、薪をどんどん足しながら
見守る──
そんな「手作業の火葬」でした。
火が弱くなれば薪を足し、夜になればランプの
灯りを頼りに焼け具合を確認したと言われて
います。
現代のように“1〜2時間で終わる火葬”ではなく、
丸一日かけて見守るような、大変な作業だった
のです。
⸻
■ 葬儀の勤行(ごんぎょう)の名残
昔の葬儀で使われていた流れが、今も「勤行の
順番」として残っています。
• 出棺勤行
• 葬場勤行
• 火屋勤行
浄土真宗など、一部の宗派では今もこの順番が
基本です。
ただし現代の葬儀会館では、出棺勤行と
葬場勤行を一つにまとめたり、火屋勤行を
火葬場で行うなど、時代に合わせて少しずつ
簡略化されています。
でも、その根底にある考え方は「故人を丁寧に
送り出す」という一点に変わりはありません。
⸻
■ 変わっても、変わらないもの
お葬式の形は大きく変わりました。
・家から会館へ
・野辺送りから霊柩車へ
・薪の火葬から近代炉へ
・村総出から家族葬へ
しかし、どれだけ時代が変わっても変わらない
ものがあります。
それは──
**「最後に、故人を想う気持ち」**です。
どんな時代も、どんな地域でも、人は大切な
方を“丁寧に送りたい”という想いで葬儀をして
きました。
その想いがある限り、葬儀の本質は今も昔も
変わらないのだと思います。
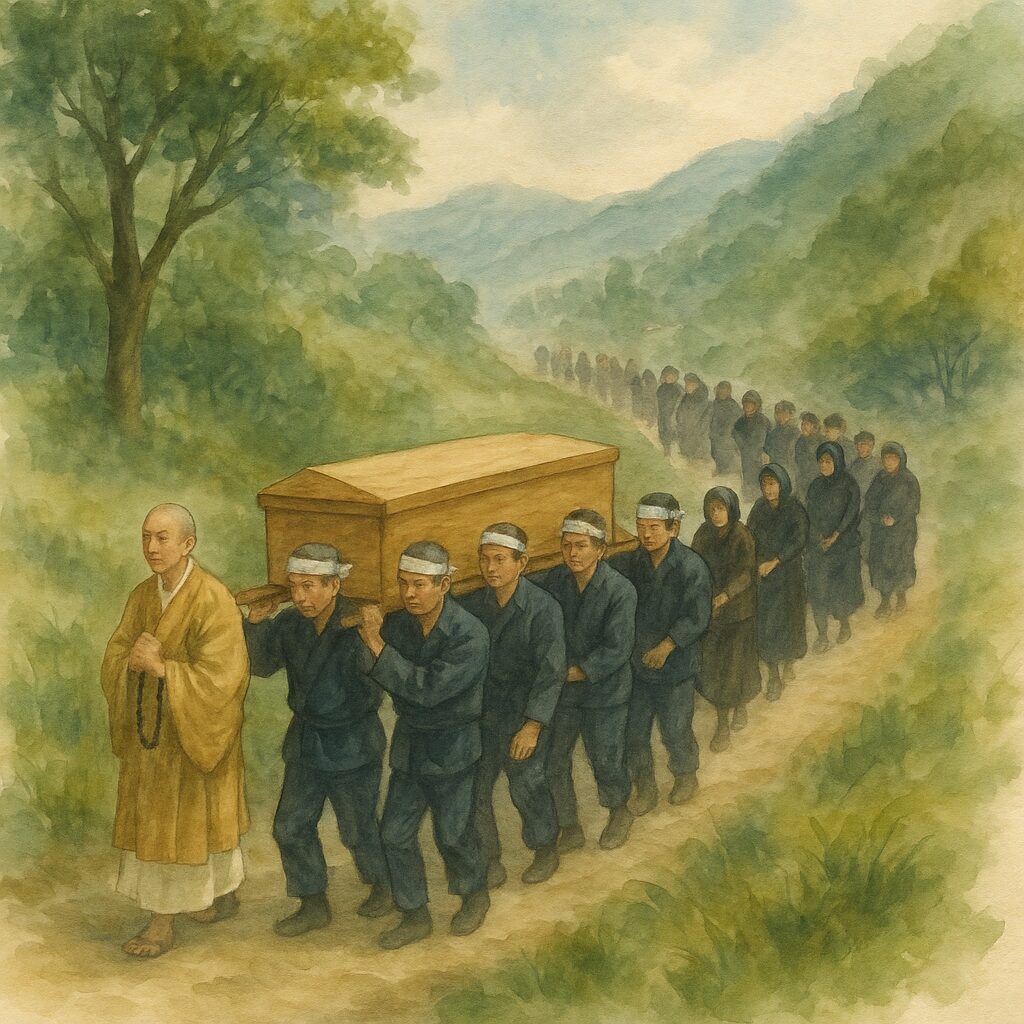
感謝。